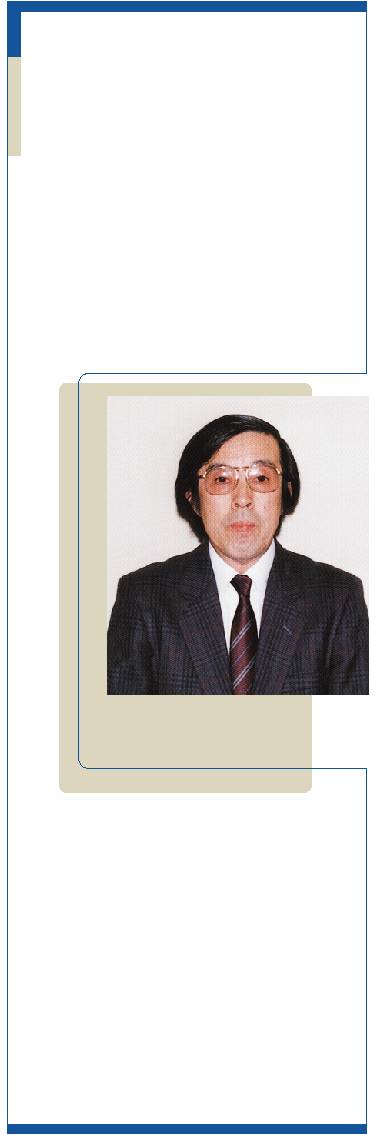ここで私が回想するのは、岡山観測所40年の丁度
真中3分の1の時期である。1973年度から科研費の補
助を受けて天体の連続スペクトルの精密測光観測を
行うために、広波長域分光測光器(通称:マルチャ
ン)を製作した。このような観測装置はすでに米
国・豪州で使われていたので、目新しいものではな
いが、いくつかの点で技術開発の突破口となるので
はないかと期待された。
1.コンピュータがやってきた!
第一に制御とデータ集録の中心に、当時やっと普
及しはじめたミニコンピュータを導入した(図3−
53参照)。それまでに東京天文台などで計算機を使
ってみた人はいたが、身近に置いて、ソフトウェア
の基礎を会得し、プログラムさえ書けば、観測・整
約などを柔軟に処理できること、ソフトウェアの重
要性が認識されるようになった。最初のミニコンは
今のパソコンに比べて桁違いに遅く(クロック周波
数がMHz程度)、プログラミングはマシン言語かア
センブラ言語かと不便ではあったが、計算機の仕組
みを理解するには適していたように思う。1979年に
は、91cm望遠鏡と測光装置のためにもう少し大き
なミニコンが設置された。これは簡単なOSでフォ
ートランが使え、フロッピー・ディスク(8インチ!)
や文字ディスプレイも付いてプログラミングが楽に
なった。さらに1984年には188cm望遠鏡の観測装置
のためにやや高速ないわゆるスーパーミニコン級の
計算機が増設されて(図3−54参照)、ほとんどの
観測が計算機に依存するようになった。しかしこの
流れは90年代に入って、ワークステーション・パソ
コンの普及とともに技術的には一新されて、新しい
時代に変った。
2.ドライ・アストロノミへ
写真に頼らない天文観測として、光電測光は以前
から行われていたが、フィルターであれスキャナー
であれ順次に測定していくので、情報量の損失が大
きかった。最初は精々10本程度の光電管からの出発
ではあったが、将来の狙いは画像検出器にあった。
1980年クーデ分光器にIDARSS検出器が設置された。
これは1次元レティコンに画像増幅装置(II)を前
置するという過渡的なものであったが、CCDの性
99
観測装置
岡山のInstrumentation
西村史朗
国立天文台名誉教授