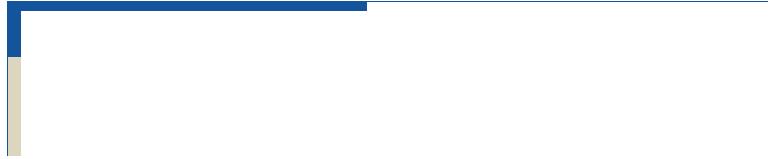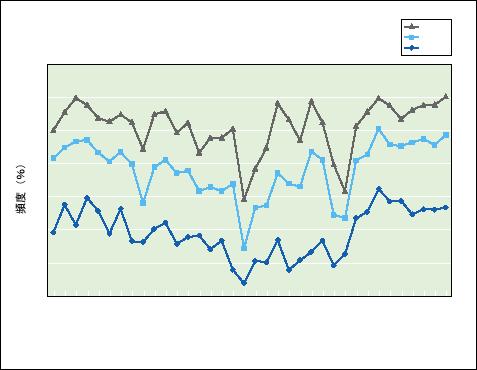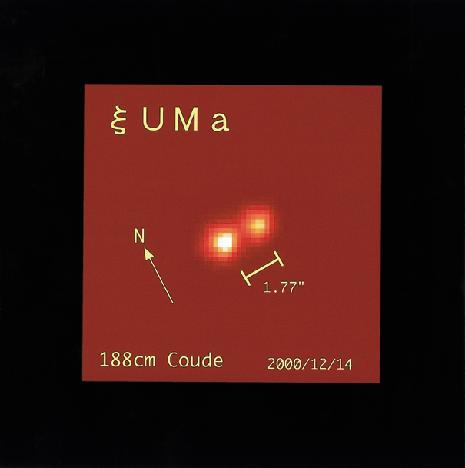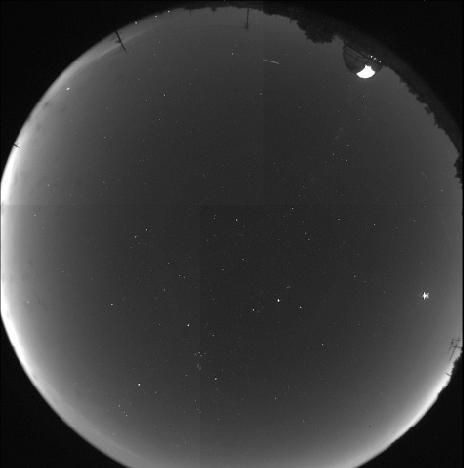40
●夜間天候
下図(図1−26)は1時間毎に記録された夜間天
候の、共同利用開始以降の11年間にわたるデータの
平均である。横軸は時間で、各月毎に上旬、中旬、
下旬と分けている。天候は快晴、晴れ、薄曇りとそ
の他(曇り、雨等)で分けたが、縦軸の頻度(%)
は0からの積算で表している。通常測光観測は快晴、
分光観測は晴れから薄曇りまで行っている。
この図から明らかなように、1年中で6月中旬か
ら7月にかけてがもっとも天気が悪い。また、9月
が次によくない。前者は梅雨時で、後者は秋雨のシ
ーズンである。逆にもっともよく晴れるのは10月で、
それに引き続く季節がよい。
また、他の地域、例えば関東地方との比較では、
晴天の分布が1年中変動が少ないことが挙げられ
る。しかしながら、個々のデータを見てみると、天
候のバラツキが非常に大きい。例えば、梅雨明けに
猛烈に晴れて80%近い晴天があったこともあるが、
秋になってもなかなか晴れずに、10%以下が続いた
こともある。
●シーイング
観測時のシーイングの状況を報告していただいて
いたが、装置や観測手法の相違から系統的な誤差が
残り、なかなか客観的な結果がえられていない。こ
のところ観測環境モニタリングの一環としてナチュ
ラルシーイングサイズの測定が行われているが、近
年は開所の頃の値(平均値2.0秒角)より明らかに改
善されている。平均値1.5秒角、最小値0.6秒角がえ
られており(図1−27参照)、これは主にドーム周
辺の樹木を伐採したことが寄与したものと考えられ
ている。
今後はドーム内の温度ムラの影響を受けるドーム
シーイングの改善が課題となる。シーイングの測定は、
ドーム内の多点温度モニターやDIMM(Differential
Image Motion Monitor)方式のシーイングモニターの
利用により本格的な改善策を施す段階にきている。
●空の明るさ
夜空の明るさは光害により開所の頃より悪化してい
る。通常の分光観測からは定量的な値が求められな
いが、以前の光電測光や、最近のスカ
イモニターからある程度信頼のできる
結果がえられる。それによると、まず
日時や気象条件により、おおきくばら
つく。一般的には、南東や南西方向の
低空で明るく(図1−28参照)、一晩
のうちでは前半夜が明るい。快晴の天
頂では、自然の夜空の明るさの3倍程
度と見積もられている。また、波長に
対しては、水銀の輝線とナトリウムの
D線が強い。このような空の明るさは
近赤外観測や高分散分光には影響が少
ないが、撮像や低分散分光には大きく
影響することがある。
第1章
最近の観測環境
夜間天候調査 ’89〜’99
70
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 (月)
薄曇り
晴れ
快晴
図1−26 平均夜間天候の頻度分布